|
|
|
|
| スケールライクに飛ばす 飛行機を見に行こう! 実機と模型の違い 実機の飛びを知ろう |
ラジコン機の飛びは?(離陸) 〃 (デッドパス) 〃 (水平直進・水平8字) 〃 (360度降下旋回) 〃 (オプショナル演技) 〃 (場周飛行〜着陸) |
これから、どのようなことに気をつければ、あなたの飛行機が本物らしく飛ぶか? 観客の皆さんに「おおっ」と言わせる飛行が出来るか? 考えていきたいと思います。
本物の飛行機をよく見たことがありますか?
ちょっと失礼だったでしょうか? 本物の飛行機をよく観察すると、RC機とはかなり違った飛びをしていることが分かるはずです。ゆったりと、安定していて、重量感があり、かなりの高速機でも「急」のつく操作は少ないはずです。
私は、一度(「見たことあるわい!」という方も再度、)飛行場に行って、1日飛行機を眺めてみることをお勧めします。きっとなにかを掴まれること請け合いです。以下に、私がお勧めする実機観察のスポットを纏めてみます。
| 飛行場又は場所 | 主な飛行機 | お勧めのポイント |
|---|---|---|
| 名古屋空港 | ジェット旅客機、軽飛行機、戦闘機、実験機、大型プロペラ機、ヘリコプタ | 国際空港でありながら、軽飛行機のの常駐が多く、ジャンボからセスナまで幅広い航空機が見られる。 三菱重工の工場があり、最新鋭の航空機が見られるのもお勧め。 |
| 岐阜基地 | 自衛隊の戦闘機、練習機、輸送機、ヘリコプタなど | 航空自衛隊の飛行開発実験団と川崎重工の工場があり、いろいろな航空機・ミサイルなどの試験を行っている。 基地祭での、異機種大編隊飛行が見もの。 |
| 小松基地 | F−15戦闘機 | F−15戦闘機の実戦部隊。 基地祭では一番迫力ある飛行をすると有名 |
| 松島基地 | T−2、T−4練習機 | 曲技飛行チーム、ブルーインパルスのホームベース。本番さながらの練習飛行が見られるかも。 練習機の基地なので、頻繁に離着陸が見られる。 |
| 但馬空港 | プロペラ曲技機(イベント時) | 曲技飛行の世界選手権を毎年誘致して実施している。 いちばんRC機に近いこれらの機体も、実機の飛びはちょっと違う、かな? |
| 調布飛行場 八尾空港 |
軽飛行機、ヘリコプタ | 軽飛行機がかなり頻繁に飛行する両飛行場、 ついでにセスナ機に乗せてもらって操縦の極意を盗んでくる、なんてのはどうでしょうか? |
| 岩国基地 | 米軍戦闘機、飛行艇PS−1 | 私は行ったことがないので強くお勧めできませんが、日本が誇る飛行艇PS−1が見られるのはここだけ?かな |
さて、皆さんは飛行場に行って実機の飛びを見てきたでしょうか? それでは質問です。
「実機と模型の一番大きな違いはなあに?」
大きさ? 速度? レイノルズ数の違いにより....ええ、ごもっとも。でも一番の違いといえば、
「パイロットが乗っているかどうか」です。
人間の強度は、機械である飛行機に比べてとてつもなく弱いものです。「Story in the Sky:じいの話」
現代の高性能の戦闘機では、パイロットのG耐性によってその性能が制限されています。逆に言えば、性能を上げるために、いかにパイロットをGから保護するかという研究が盛んなほどです。
話が脱線してしまいました。つまり、実機では、パイロットが失神してしまうような急激な旋回や、頭に血が上るような背面飛行の連続などは通常ありえないのです。(もちろん、一部の曲技専用機や航空ショーでは違いますが)
ほらほら、そこの貴方、貴方の飛ばす飛行機は「常に」そのような操縦をしていませんか?
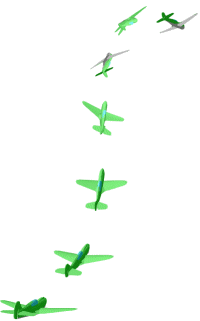
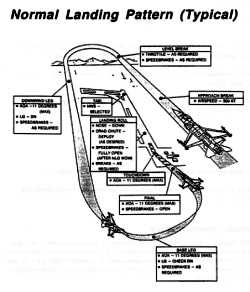 最終進入時の降下角度は、どのような飛行機でも約3度です。これは、ILS(計器着陸装置)の誘導電波の角度でもあります。場周飛行から着陸する場合、バンクは30度以内で旋回し、最終旋回を終わったら約3度の一定の降下角度で進入します。エンジンは絞りきった状態ではありません。ラジコン機で言えば、「パワーで吊って」持ってくる感じです。そうでないと、パスが高くなったときの修正が出来ません。接地直前にはじめてパワーをアイドルにし、緩やかに引き起こして着陸します。
最終進入時の降下角度は、どのような飛行機でも約3度です。これは、ILS(計器着陸装置)の誘導電波の角度でもあります。場周飛行から着陸する場合、バンクは30度以内で旋回し、最終旋回を終わったら約3度の一定の降下角度で進入します。エンジンは絞りきった状態ではありません。ラジコン機で言えば、「パワーで吊って」持ってくる感じです。そうでないと、パスが高くなったときの修正が出来ません。接地直前にはじめてパワーをアイドルにし、緩やかに引き起こして着陸します。
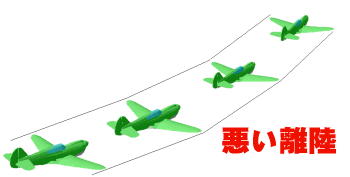 離陸は全ての飛行の始まりです。これが決まるかどうかで飛行に対する印象が全く違ってきます。
離陸は全ての飛行の始まりです。これが決まるかどうかで飛行に対する印象が全く違ってきます。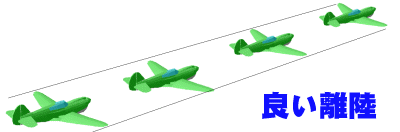
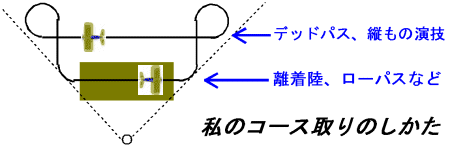
| 小型機・輸送機 | 戦闘機 | ジェット戦闘機 | |
| 基準バンク角 | 約30度 | 約45度 | 約60度 |
| ロールレート(通常) | 3−5度/秒 | 10度/秒 | 30度/秒 |
お客さんを乗せる飛行機、大型機ほどロールレートは遅く、バンク角は小さくなります。逆にジェット戦闘機は比較的RC機に近いと思います。
旋回中は、なるだけ一定バンク角でスムーズに回ります。きれいな8の字を描けるように、風に流されるのを考慮してバンク角を調整します。
進入したのと同一の経路、高度で審査員の目前を通過できれば、GOODです。
この演技に入る前には、高度をとらねばなりません。
ただし、いつの間にか高度が上がったという風でなく、パワーを増し、上昇姿勢として、必要な高度まで上昇しました、という姿勢が必要と思います。(飛行のメリハリ)
飛行経路は、水平直線飛行で進入したと同じ経路です。高度が高いと、その分遠くを飛行させる人が結構いますので注意してください。
演技開始と同時にパワーを絞り、「これから降下するぞ」という姿勢を見せます。ダウンを打つのではありません。バンクをとり、自然に降下を開始してください。8字飛行と同様、風に流されないよう、バンク角を調整して正確な360度の真円を描きます。ロールアウトと同時に水平直線飛行に戻し、演技は終了です。
オプショナル演技をすべて解説するのは困難です。
しかし、共通する考え方はあります。
まず、曲技系の演技(ロール、ループ、インメルマンなど)を、巡航状態からあっさり始められるほどパワーのある実機は少ない、ということです。
これらの演技を始めるときは、いかにも「加速しましたよ」というふりをします。(実際に加速します)軽飛行機タイプや古典機なら、軽くダイブするのがよいでしょう。ただし、シャンデルは違います。これは水平飛行の巡航状態から行う演技です。よって、非曲技機が行ってもかまいません。
当たり前のことですが、旅客機や輸送機でこれら曲技系の演技を行ってはなりません。(観客には受けるかもしれませんが) 実機の旅客機の[G]制限はたったの2.5Gです。もし、旅客機がループを行ったら多分、空中分解でしょう。
水平系の演技(3角形/4辺形サーキット、ローパスなど)は「水平直線飛行」と同じ。あくまで一定高度で、ロールレート、バンク角などに気をつけて飛行します。演技が単調になりやすいので、あくまで直線は直線に、旋回の入りと抜けはぴたりとバンクを止めるよう、メリハリをつけましょう。
着陸進入系の演技(オーバーシュート、タッチアンドゴー)では、離陸、着陸(後述)両方の注意点が適用されます。フラップ、脚などを操作する場合、スイッチ操作で機体が揺れないように気をつけてください。私はタッチアンドゴーの最中にフラップのスイッチを触る自信はありません。よって、触らなくても良いように、オートランディング・モードをセットし、スロットルと連動させています。
余計なことですが、「オーバーシュート」の演技で接地しないようにしてください。この演技の最低高度は3mです。以前、私が「オーバーシュート」をコールして不用意に接地してしまい。「これは違う演技をしたんだから0点だわなー」と言われたことがあります。あたりまえですよね、皆さんはこんなミスをしないように....
 さて、いよいよ着陸です。演技の最後を締めくくる、華麗な着陸を演じたいものです。では、どのような進入・着陸が良いのでしょうか。
さて、いよいよ着陸です。演技の最後を締めくくる、華麗な着陸を演じたいものです。では、どのような進入・着陸が良いのでしょうか。
まずは場周飛行、何度も言うようにあくまで一定高度でスムーズに飛行します。高度は水平直線飛行と同じ5m程度がよいでしょう。飛行速度は水平直ある程度落としておかないと、あとの速度処理が難しいでしょう。ダウンウインド・レグ(風下に向いたとき)脚やフラップを下げます。飛行経路が変化しないよう、十分注意してください。
脚が降りたらいよいよ着陸です。ベースレグからは一定の角度で進入します。角度は前述のように、どんな飛行機も約3度です。かなり浅い角度です。高い高度から突っ込んでこないよう気をつけてください。速度はだいぶ落として、パワーで吊ってくる感じです。でないと、パスが高くなった場合の修正ができません。このため、普段から自分の飛行機の失速速度、エレベーターの引き具合を良く把握しておく必要があります。失速速度に近いので、操舵は十分気をつけて、スムーズに行います。
一般的に、失速を懸念するあまり、大変速い速度で、パワー・アイドルで1発勝負! という着陸が多いようです。これではいい着陸が出来るはずがありません。スムーズで、急激な操舵をしなければ恐いことはありません。速度を十分落とし、接地直前までパワーを残しておくのが理想です。一定の角度で接地点に向けて降下させ、接地直前に滑らかにパワーをアイドルまで絞りながら引き起こします。
引き起こしは、沈下率を止め、ソフトに着陸するために行います。決して、着陸の姿勢を作るためではありません。速度が多いのに、無理に3点着陸をしようと思っても、波状飛行となったり、フローティングして、いつまでも接地させることが出来ません。
接地後も、飛行機が止まるまで気を抜いてはいけません。横風で煽られないよう、エルロンとラダーで方向保持をし、行き足が落ちてきたら、鼻つき防止のためエレベーターはフルアップにしましょう。
滑走路に飛行機をまっすぐ停止させ、「フィニッシュ」と高らかにコールするのを、お忘れ無く。
「実機らしい飛び」について、離陸から着陸まで順を追って説明してみましたが、如何だったでしょうか?
自分ではわかっていても、なかなか上手に出来ないことばかりですよね。
飛行機を綺麗に作ることはとても大切です。ただ、もう少し、ほんの少しこれを飛ばし込んで機体特有の癖をつかみ、自信を持って飛ばせるようになりたいものです。